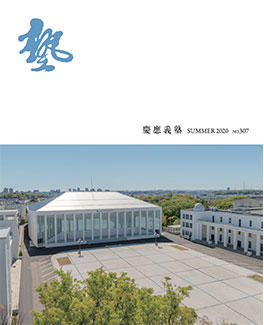「塾」2020 Summer (No. 307)
標記題名の記事を掲載していただいた。興味を持たれた方はこちらまで。本来なら大学のキャンパスでふつうに手にとることができるのだが、今は事情が違うので、ここで紹介させていただこうかと。
注目の投稿
2020/07/16
2020/07/10
三田の先生と氷川の御前様
丸山真男 1986『「文明論之概略」を読む』上中下(岩波新書)
あるとき人と話をしていて、丸山真男の名前が出た。それって誰だっけ、本持ってたかな、と記憶をたどりつつ書棚を見ると、新書を雑然と並べてあった場所に見つけた。持っていたのは『「文明論之概略」を読む』だった。
だいぶ前に手に取ってそれきりだったので、今日の医者の待ち時間に再度読み始めた(1時間半くらい待たされたのでだいぶ進んだ)。
丸山氏のこの本、「読み手」のほうも一流なので、古典が生き生きと立ち上がってきて、一粒で二度おいしい。福沢先生自身は多面的で、一つの尺度では割り切れないと思うが、それだけに、丸山氏の筋の通ったフィルターを通して選ばれた「文明論之概略」からの引用は、独自の意義を持つと思う。
「人、或は云わん、人類の約束は唯自国の独立のみを以て目的と為す可からず、尚別に永遠高尚の極に眼を着す可しと。此の言、真に然り。人間智徳の極度に至りては、其の期する所、固より高遠にして、一国独立等の細事に介々たる可からず。僅に他国の軽侮を免かるるを見て、直に之れを文明と名づく可からざるは論を俟たずと雖ども、今の世界の有様に於て、国と国の交際には、未だ此の高遠の事を談ず可からず、若し之れを談ずる者あれば、之れを迂闊空遠と云はざるを得ず。」
しばしば格言のような形で引かれる、「一国独立」という理念を「細事」と言ってのけるのを見て一瞬ギョッとしたが、前後を見ると、それは「智徳の極度に至りては」というIFの世界でのことだとわかる。「其の期する所、固より高遠」というのもなるほど。それは一種のユートピア、老子のいう小国寡民の世界か。そんな時が来るのか、と言われれば、安易にイエスとも言えないが、1000年もあれば何とかなるんじゃないかと思ったりーー「たとえそれが那由他の彼方でも 俺には充分に過ぎる」(アンデルセン)。
それはさておき、原文に戻ると、「今の世界の有様に於て」考えてみれば、無自覚に理想主義を語れるような状況ではなく、そんな話をする者がいたら「迂闊空遠」である、と。遠い理想と目に見える現実の両方をにらむ、というのは決して易しいことではない。これは現代のわれわれにとってもリアルな課題である。
そして下巻へと進む。もうすぐ読了まできた。線を引いて記憶にとどめたくなるパッセージが山盛り。例えば...
「国と国との交際に至りては唯二箇条あるのみ。云く、平時は物を売買して互ひに利を争ひ、事あれば武器を以て相殺すなり。言葉を替えて云へば、今の世界は商売と戦争の世の中と名づくるも可なり。(中略)今の世界に行わるゝ各国の戦争と貿易との情実を尋れば、宗教愛敵の極意より由て来りしものとは、万々思ふ可らざるなり」
福沢先生はよくリアリストと言われるが、こりゃもうアカギなみのニヒリストの域と紙一重ではないか。上の「相殺」は「打ち消す」ではなく本当の殺し合いである。これが文明開化でヒャッハーしていたころの明治初期に書かれたというのも、実にとんでもない話である...と最初思ったが、ひょっとしたら幕末・維新を生き延びた人々にとってはむしろ当然のことだったかも。
そして丸山氏の曰く...
「福沢に戻るならば、西洋から学んだ「天地の公道」をたんに「建て前」とするだけでなく、本当に「慕う」ことによって、まさにそれを、権力政治で立ち向かってくる列強の胸にさかさまにつきつける資格ができるはずです。さあ、お前たちは国境を撤廃し、政府権力を廃止する覚悟と「術」(方法)があるか。もしインターナショナリズムの行きつくところを知らないで言っているのなら、「結構人の議論」であり、またもし知りながら「情実」を美化しようとするなら偽善ではないか、と迫る福沢の鋭いまなざしが、このあたりの文章から浮かんでくるようです」下巻p. 240
こういう読み込みをする丸山氏もすごい。なお「結構人の議論」とはお人好しのご都合主義だそうで(すなわち脳内お花畑)。この本が出たのが1986年で、冷戦末期なのだが、インターナショナリズムをグローバリズムと置き換えれば、むしろ冷戦態勢崩壊後の現代にこそあてはまる。この人は形骸化した左翼とは違う、自由で強靭な思考の持ち主だったということがうかがわれる。
木下直之. 2013『戦争という見世物 日清戦争祝捷大会潜入記』(ミネルヴァ書房)
最初に題名を見た時は(「捷」は「勝」だそうで)、数年や数十年のスケールでメディアの報道を追っていくスタイルか、それともいろんなケーススタディをまとめた本なのかと思ったが、そうではなくて日清戦争当時の明治のある一日、その一点のみに絞り込んで、当時の記録を執拗に掘り起こした再現ドキュメンタリーになっている。精度の高い個別研究は一般性・普遍性にたどりつく最良の道だということを再認識。
で、いきなり前書きで唸った。といっても著者の文章にでなく、この本が描き出している同時代にはまだ存命だった、氷川の御前様の述壊に...
「日清戦争はおれは大反対だつたよ。なぜかつて、兄弟喧嘩だもの犬も喰わないヂやないか。たとへ日本が勝ってもドーなる。支那はやはりスフインクスとして外国の奴らが分からぬに限る。支那の実力が分かつたら最後、欧米からドシドシ押し掛けて来る。ツマリ欧米人が分からないうちに、日本は支那と組んで商業なり工業なり鉄道なりやるに限るよ。」p. viii
氷川清話は読んだはずだが、まるっきり内容が頭に残ってなかったw 御前様、中国との関係を兄弟といい、これに続く箇所では「昔時から日本の師」と言っているが、その実、清国が張り子の虎だとバレないうちに商売に励めとおっしゃる。今にして思えばその通りだったのだが、あの時代にこうして見通す、これまたニヒリズムと紙一重の眼力、さすがに幕末の修羅場をその最前線で生き抜いた(どころじゃなく、自ら幕引きの任を負った)勝海舟ならでは。
思えば当時の清国は西洋の帝国主義にとって最後のフロンティアで、わけても最新にして最強の列強たる米国の狙い目だったのであろう。太平洋戦争の惨禍に至る伏線はたくさんあれど、欧米の列強がそこまで中国大陸の利権に執着すると当時の日本人が思わなかったことはその一つだったかもしれない。列強はありあまるほどの領土と富を独占していたのだから、東洋の隅っこでコソコソやってるぶんにはお目こぼししてもらえるだろうと高をくくっていたのが間違いだった...と今さら思っても仕方ないけれど。ちなみに御前様、上記の引用のすぐ後で、「ともあれ、日本人もあまり戦争に勝ったなどと威張って居ると、後で大変な目にあふヨ。剣や鉄砲の戦争には勝っても、経済上の戦争に負けると、国は仕方がなくなるヨ」とさらに日本の行く末を見通した言があり、流石である。
もしも日清戦争が起きず、適当なところで手打ちをしていたらその後の歴史はどうなっていただろうか。日露戦争は勃発せず、ロシア革命は成就せず、毛沢東は台頭せず、などと空想するのは面白いが、あまり妄言を垂れ流してもしょうがないので、今日はここまで。
[某氏1からのレス]
そういうifを楽しむのが仮想戦記の醍醐味だったんですがねぇ。どこで間違えたのやら、もはや瀕死のジャンルに・・・(T_T) 似たようなif世界物として【蒼海の世紀】が面白いっすよ。
[某氏2からのレス]
(初出:July 2014 & January 2015)
あるとき人と話をしていて、丸山真男の名前が出た。それって誰だっけ、本持ってたかな、と記憶をたどりつつ書棚を見ると、新書を雑然と並べてあった場所に見つけた。持っていたのは『「文明論之概略」を読む』だった。
だいぶ前に手に取ってそれきりだったので、今日の医者の待ち時間に再度読み始めた(1時間半くらい待たされたのでだいぶ進んだ)。
丸山氏のこの本、「読み手」のほうも一流なので、古典が生き生きと立ち上がってきて、一粒で二度おいしい。福沢先生自身は多面的で、一つの尺度では割り切れないと思うが、それだけに、丸山氏の筋の通ったフィルターを通して選ばれた「文明論之概略」からの引用は、独自の意義を持つと思う。
「人、或は云わん、人類の約束は唯自国の独立のみを以て目的と為す可からず、尚別に永遠高尚の極に眼を着す可しと。此の言、真に然り。人間智徳の極度に至りては、其の期する所、固より高遠にして、一国独立等の細事に介々たる可からず。僅に他国の軽侮を免かるるを見て、直に之れを文明と名づく可からざるは論を俟たずと雖ども、今の世界の有様に於て、国と国の交際には、未だ此の高遠の事を談ず可からず、若し之れを談ずる者あれば、之れを迂闊空遠と云はざるを得ず。」
しばしば格言のような形で引かれる、「一国独立」という理念を「細事」と言ってのけるのを見て一瞬ギョッとしたが、前後を見ると、それは「智徳の極度に至りては」というIFの世界でのことだとわかる。「其の期する所、固より高遠」というのもなるほど。それは一種のユートピア、老子のいう小国寡民の世界か。そんな時が来るのか、と言われれば、安易にイエスとも言えないが、1000年もあれば何とかなるんじゃないかと思ったりーー「たとえそれが那由他の彼方でも 俺には充分に過ぎる」(アンデルセン)。
それはさておき、原文に戻ると、「今の世界の有様に於て」考えてみれば、無自覚に理想主義を語れるような状況ではなく、そんな話をする者がいたら「迂闊空遠」である、と。遠い理想と目に見える現実の両方をにらむ、というのは決して易しいことではない。これは現代のわれわれにとってもリアルな課題である。
そして下巻へと進む。もうすぐ読了まできた。線を引いて記憶にとどめたくなるパッセージが山盛り。例えば...
「国と国との交際に至りては唯二箇条あるのみ。云く、平時は物を売買して互ひに利を争ひ、事あれば武器を以て相殺すなり。言葉を替えて云へば、今の世界は商売と戦争の世の中と名づくるも可なり。(中略)今の世界に行わるゝ各国の戦争と貿易との情実を尋れば、宗教愛敵の極意より由て来りしものとは、万々思ふ可らざるなり」
福沢先生はよくリアリストと言われるが、こりゃもうアカギなみのニヒリストの域と紙一重ではないか。上の「相殺」は「打ち消す」ではなく本当の殺し合いである。これが文明開化でヒャッハーしていたころの明治初期に書かれたというのも、実にとんでもない話である...と最初思ったが、ひょっとしたら幕末・維新を生き延びた人々にとってはむしろ当然のことだったかも。
そして丸山氏の曰く...
「福沢に戻るならば、西洋から学んだ「天地の公道」をたんに「建て前」とするだけでなく、本当に「慕う」ことによって、まさにそれを、権力政治で立ち向かってくる列強の胸にさかさまにつきつける資格ができるはずです。さあ、お前たちは国境を撤廃し、政府権力を廃止する覚悟と「術」(方法)があるか。もしインターナショナリズムの行きつくところを知らないで言っているのなら、「結構人の議論」であり、またもし知りながら「情実」を美化しようとするなら偽善ではないか、と迫る福沢の鋭いまなざしが、このあたりの文章から浮かんでくるようです」下巻p. 240
こういう読み込みをする丸山氏もすごい。なお「結構人の議論」とはお人好しのご都合主義だそうで(すなわち脳内お花畑)。この本が出たのが1986年で、冷戦末期なのだが、インターナショナリズムをグローバリズムと置き換えれば、むしろ冷戦態勢崩壊後の現代にこそあてはまる。この人は形骸化した左翼とは違う、自由で強靭な思考の持ち主だったということがうかがわれる。
木下直之. 2013『戦争という見世物 日清戦争祝捷大会潜入記』(ミネルヴァ書房)
最初に題名を見た時は(「捷」は「勝」だそうで)、数年や数十年のスケールでメディアの報道を追っていくスタイルか、それともいろんなケーススタディをまとめた本なのかと思ったが、そうではなくて日清戦争当時の明治のある一日、その一点のみに絞り込んで、当時の記録を執拗に掘り起こした再現ドキュメンタリーになっている。精度の高い個別研究は一般性・普遍性にたどりつく最良の道だということを再認識。
で、いきなり前書きで唸った。といっても著者の文章にでなく、この本が描き出している同時代にはまだ存命だった、氷川の御前様の述壊に...
「日清戦争はおれは大反対だつたよ。なぜかつて、兄弟喧嘩だもの犬も喰わないヂやないか。たとへ日本が勝ってもドーなる。支那はやはりスフインクスとして外国の奴らが分からぬに限る。支那の実力が分かつたら最後、欧米からドシドシ押し掛けて来る。ツマリ欧米人が分からないうちに、日本は支那と組んで商業なり工業なり鉄道なりやるに限るよ。」p. viii
氷川清話は読んだはずだが、まるっきり内容が頭に残ってなかったw 御前様、中国との関係を兄弟といい、これに続く箇所では「昔時から日本の師」と言っているが、その実、清国が張り子の虎だとバレないうちに商売に励めとおっしゃる。今にして思えばその通りだったのだが、あの時代にこうして見通す、これまたニヒリズムと紙一重の眼力、さすがに幕末の修羅場をその最前線で生き抜いた(どころじゃなく、自ら幕引きの任を負った)勝海舟ならでは。
思えば当時の清国は西洋の帝国主義にとって最後のフロンティアで、わけても最新にして最強の列強たる米国の狙い目だったのであろう。太平洋戦争の惨禍に至る伏線はたくさんあれど、欧米の列強がそこまで中国大陸の利権に執着すると当時の日本人が思わなかったことはその一つだったかもしれない。列強はありあまるほどの領土と富を独占していたのだから、東洋の隅っこでコソコソやってるぶんにはお目こぼししてもらえるだろうと高をくくっていたのが間違いだった...と今さら思っても仕方ないけれど。ちなみに御前様、上記の引用のすぐ後で、「ともあれ、日本人もあまり戦争に勝ったなどと威張って居ると、後で大変な目にあふヨ。剣や鉄砲の戦争には勝っても、経済上の戦争に負けると、国は仕方がなくなるヨ」とさらに日本の行く末を見通した言があり、流石である。
もしも日清戦争が起きず、適当なところで手打ちをしていたらその後の歴史はどうなっていただろうか。日露戦争は勃発せず、ロシア革命は成就せず、毛沢東は台頭せず、などと空想するのは面白いが、あまり妄言を垂れ流してもしょうがないので、今日はここまで。
[某氏1からのレス]
そういうifを楽しむのが仮想戦記の醍醐味だったんですがねぇ。どこで間違えたのやら、もはや瀕死のジャンルに・・・(T_T) 似たようなif世界物として【蒼海の世紀】が面白いっすよ。
[某氏2からのレス]
日清戦争前後の対中外交にあったとも言えそうですわな。>この辺のをネタにして月刊アフタヌーンで安彦さんがまた描いてますな。 昨日生協で立ち読みしたらラスト近くで安さんが石炭運んで悪態ついてました^^
(初出:July 2014 & January 2015)
2020/07/05
NICEな論文
他エントリーで紹介した、『認知言語学の羽ばたき』、その冒頭にある松本曜氏の文章の中に、論文を書く上で示唆的な部分があると紹介時に書いた。今は七月、ちょうど塾生諸氏も期末レポートにとりかかる時期でもあり、ここで紹介したい。
「良い論文とされるものには、4つ要素がある」(p. 4)と松本氏は説く。これらの要素とはN=new(新しい知見), I=integrated(まとまり、一貫性), C=clear(明晰さ), E=empirical(経験科学としての妥当性)、頭文字をとってNICEになるという次第。とても分かりやすいアドバイスである。
多少補足すれば、新しさというのは多分に相対的なものである。学生のレポートでも、まずは自分にとって新鮮に感じられる事柄を報告してほしい。もちろん、新発見だと思ったことが、さらに調べたらよく知られていることだった、ということは誰にでもある。先行研究にあたる理由は、研究のアイデアを得るためだけでなく、自分の考えがどのくらい新しいかを確かめるためでもある。同時に、自分が提示する事柄には客観性の保証が求められることも念頭に置いてほしい。「自分がそう思ったから」では弱いので、複数人への聞き取りやアンケート、コーパス利用による数値的な偏りの認定、翻訳を利用した対照言語分析、条件をコントロールした実験(アンケート調査も設定次第では実験と同じ)などを採り入れることができれば素晴らしい。
それでは皆様、Have a NICE weekend!
「良い論文とされるものには、4つ要素がある」(p. 4)と松本氏は説く。これらの要素とはN=new(新しい知見), I=integrated(まとまり、一貫性), C=clear(明晰さ), E=empirical(経験科学としての妥当性)、頭文字をとってNICEになるという次第。とても分かりやすいアドバイスである。
多少補足すれば、新しさというのは多分に相対的なものである。学生のレポートでも、まずは自分にとって新鮮に感じられる事柄を報告してほしい。もちろん、新発見だと思ったことが、さらに調べたらよく知られていることだった、ということは誰にでもある。先行研究にあたる理由は、研究のアイデアを得るためだけでなく、自分の考えがどのくらい新しいかを確かめるためでもある。同時に、自分が提示する事柄には客観性の保証が求められることも念頭に置いてほしい。「自分がそう思ったから」では弱いので、複数人への聞き取りやアンケート、コーパス利用による数値的な偏りの認定、翻訳を利用した対照言語分析、条件をコントロールした実験(アンケート調査も設定次第では実験と同じ)などを採り入れることができれば素晴らしい。
それでは皆様、Have a NICE weekend!
登録:
コメント (Atom)