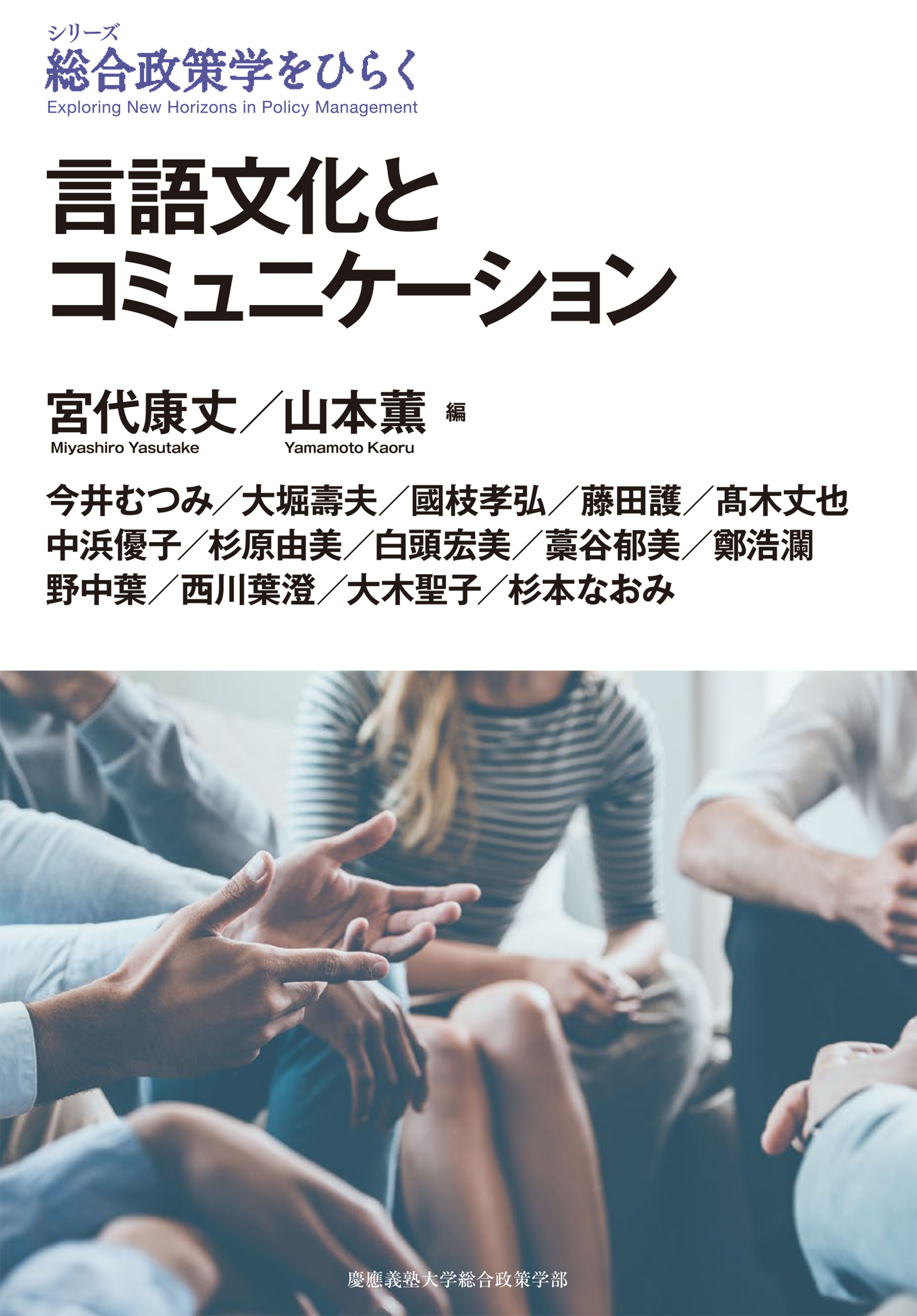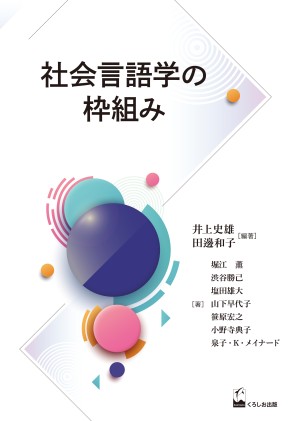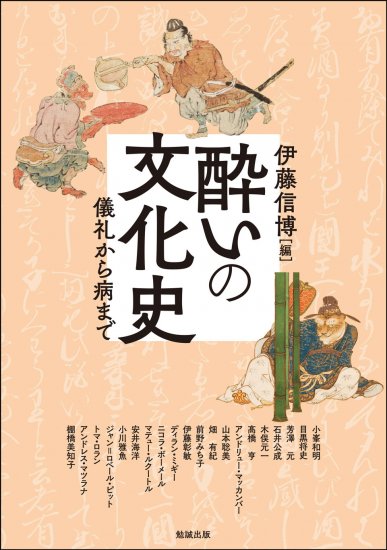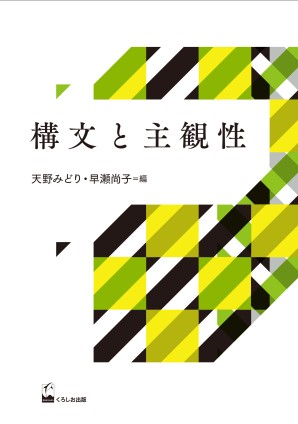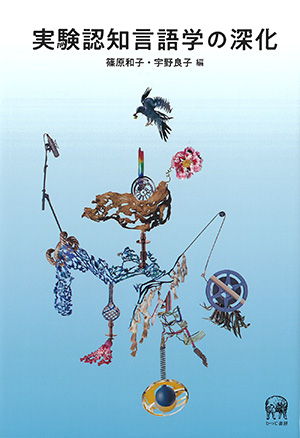【2025年3月の定年退職に伴い、研究会は閉店しました。認知・機能言語学の入門者向けの情報ソースとして残しておきます】
ようこそ、言語科学の研究会へ! 言語研究の参考となるような情報は、随時Tidbitsタグをつけてここのサイトに公開していきます。また、認知言語学関連のメタリンクも用意しました。卒業プロジェクトに取り組んでいる人、これからテーマを探して深める人、それぞれだと思われるので、進度に合わせて授業時間を有効活用したいと思います。
- 「構文研究メモ」を公開しました。このメモで取り上げているようなことを研究会では行います。研究会に新規加入の際は、春学期で取り組む構文に当たりをつけておくとより楽しく研究できると思います。
- 日本では優れた「語法研究」の伝統があります。今日私たちが非常に優れた、情報量の多い辞書が利用できるのも、英語参考書などで語法の細かい使い分けについて丁寧な解説がされるのも、この分野の先人のお陰です。その集大成が、『英語語法大辞典』第1-4集, 大修館書店。語学好きならぜひ現物を手にとってください。また、個人による語法研究の本もたくさん出ています。とりあえず、私の本棚にあるものをいくつか紹介。
- 英語語法研究といえば、洞察の鋭さと用例の周到さにおいて最高位にあるのがこの一冊(残念ながら絶版だが図書館にはある)。
- 郡司隆男・西垣内泰介(編)(2004)『ことばの科学ハンドブック』研究社
- 佐久間淳一・町田健・加藤重広(2004)『言語学入門:これから始める人のための入門書』研究社
- 大津由紀雄(編)(2009)『はじめて学ぶ言語学:ことばの世界をさぐる17章』ミネルヴァ書房
- 斎藤純男(2010)『言語学入門』三省堂
- 窪薗晴夫(編)(2019)『よくわかる言語学』ミネルヴァ書房
- 斎藤純男・田口善久・西村義樹(2015)『明解言語学辞典』三省堂
- 西村義樹・野矢茂樹(2013)『言語学の教室』中央公論新社
- 大堀壽夫(2002)『認知言語学』東京大学出版会
- 籾山洋介(2014)『日本語研究のための認知言語学』研究社
- 野村益寛(2014)『ファンダメンタル認知言語学』ひつじ書房
- 池上嘉彦・河上誓作・山梨正明(監修)シリーズ認知言語学入門
- 辻幸夫(編)(2003)『認知言語学への招待』シリーズ認知言語学入門1 大修館
- 吉村公宏(編)(2003)『認知音韻・形態論』シリーズ認知言語学入門2 大修館
- 西村義樹(編)(2018)『認知文法論1』シリーズ認知言語学入門3 大修館
- 中村芳久(編)(2004)『認知文法論2』シリーズ認知言語学入門4 大修館
- 松本曜(編)(2003)『認知意味論』シリーズ認知言語学入門5 大修館
- 大堀壽夫(編)(2004)『認知コミュニケーション論』シリーズ認知言語学入門6 大修館
- 中本敬子・李在鎬(編) (2011)『認知言語学研究の方法:内省・コーパス・実験』ひつじ書房
- 辻幸夫(編)(2013)『新編認知言語学キーワード事典』研究社
- 辻幸夫他(編)(2019)『認知言語学大事典』朝倉書店
- 加藤重広・澤田淳(編)2020『はじめての語用論−−基礎から応用まで』 研究社
- 加藤重広・滝浦真人(編)2016『語用論研究法ガイドブック』ひつじ書房
- 小山亘. 2012『コミュニケーション論のまなざし』三元社
- 大橋理枝・根橋玲子. 2019『コミュニケーション学入門』放送大学
4)研究計画の立て方やデータ分析の方法について解説した本も読んでおくとよいでしょう。上に挙げた中本敬子・李在鎬(編) (2011)『認知言語学研究の方法』の他にいくつか紹介します。藤村・滝沢は全般にわたる解説、坊農・高梨は会話の分析を中心にしたものです。Wray & Bloomerはテーマ探しから始めて(言語研究の各分野の紹介つき)、データ集めと分析、さらには研究の発表のまとめ方まで親切に解説しています。Litosselitiは言語研究のさまざまな方法論(質的、量的、聞き取り調査、コーパス分析、等)を紹介したものです。自分が使いたい方法について詳しく学ぶのに役立ちます。Hatch & Lazaratonは新版が出ていないのが残念ですが、基礎的な統計的分析の方法を広く扱っています。これも自分の目的に合った方法を解説した部分を選んで読むとよいです。
- 藤村逸子・滝沢直宏 (編) (2011) 『言語研究の技法』. ひつじ書房.
- 坊農真弓・高梨克也 (編) (2009) 『多人数インタラクションの分析方法』. オーム社.
- Wray, A. & A. Bloomer (2012, 3rd ed.) Projects in Linguistics and Language Studies. London: Routledge.
- Litosseliti, Lia (ed.) (2018, 2nd ed.) Research Methods in Linguistics. London: Bloomsbury.
- Hatch, E. & A. Lazaraton (1991) The Research Manual: Design and Statistics for Applied Linguistics. NY: Newbury House
5)論文の書式について。さまざまな学会で「投稿規定」の一部として論文の書式=style sheetを決めているので、一つのスタイルに決めて、それに従うこと。例えば英語だと日本英語学会の投稿規定ページは詳しい規定があります(最下部にサンプルのpdfファイルあり)。海外ではAmerican Psychological AssociationやModern Language Associatonのstyle sheetがよく知られています。どちらも正式のガイドブックは有料ですが、ネット上では簡略化した紹介があるので各自で参照することをすすめます。日本語でも多くの学会が公式サイトにスタイルシートを載せています。自分で関心をもった研究がよく出てくる学会のスタイルシートを使うとよいでしょう。出版社の中には自社仕様のものを用意しているところがあります。ひつじ書房の執筆要項はその一つ。もちろん、卒業論文は表紙がついたり、大学固有の規定もあるので、それは各自で確認してください。
本研究会では、これまで次の卒業プロジェクトが提出されています。
- 若者言葉における重複表現について
- 美術への専門性が絵画作品への言及にもたらす影響
- SNSにおける『界隈』に対する考察~オンラインコミュニティとしての観点・認知言語学の観点から~
- フレーム意味論に基づく「オタク」の意味分析--「オタク」の意味拡張に関する考察[優秀卒業プロジェクト]
- 身体醜形概念と(幼少期の)親子関係の関連
- 身体を使ったイディオムと身体論の関係性について
- 映画キャッチコピーにおける句読点使用の変化と背景考察
- 在日外国人が漢字に興味を持つ理由を明らかにする
- 言葉の力から見る『KEIO日本一』
- インスタグラム広告における「いいね」獲得方法
- 化粧品におけるカラーネーム考察〜認知言語学的視点から〜
- SNS 言論が携帯業界の企業活動に与える社会的影響に関する分析
- 多義語における意味拡張を理解することによる記憶定着への影響とそこから考える日本の英語教育
- On the Multimodality of English [ADV and ADV] Construction: A Collostructional Approach[優秀卒業プロジェクト]
- インターネットスラングの認知言語学的考察〜「親ガチャ」を例に〜
- 日本語におけるコロナウイルスに対する戦争メタファー
- 『不思議の国のアリス』からみる翻訳の日英比較--オノマトペを中心に翻訳者が作品に与える影響について
- 日本語を第二言語とする日本語使用者の口語特徴の考察
- バナー広告におけるインプレッション効果を 促進する視覚情報と言語表現のシナジー効果
- インスタグラムにおけるキャプションの影響力〜認知言語学的観点からインスタグラムを紐解く〜
- 比喩表現における日米言語の比較
- 本当に新型コロナウィルスは日本国内で終息を迎えるのか? 〜Twitter を用いたウィズコロナの動向分析〜
- 多義語のパラドックスに関する考察−認知言語学の視点から− [優秀卒業プロジェクト]
- スポーツの場におけるミスコミュニケーションの分析
- チームスポーツにおけるコミュニケーション−−複雑なミスの発生要因の分析と解消の考察−−
- デザインプロセスにおける言葉の役割と創造性について
- プロとアマチュア記者の記事にはどのような言語学的な違いがあるのか・良い記事にはどのような特徴があるのか
- 現代版弁論術のすすめ−−人を説得するための技術−−
- 言語学的観点から見た漫才のツッコミ
- 動物キャラクターのステレオタイプと役割語を検証−−アニメーション映画「バケモノの子」を用いて−−
- 反復練習による、役者の演技の変化について
- 漫画における感情表現の日・英翻訳比較研究
- 歴代「角川短歌賞」受賞作にみる現代短歌と家族観
- SNSコミュニケーションによる引きこもりのストレス緩和について
- イタリア映画の日本字幕における技法とコツとは
- ノンバーバルコミュニケーションにおける「間」の感性情報心理学・周辺言語
- 人が表情を読み取るとき、文字と音声情報はどのような影響を与えるのか
- 認知言語学×スポーツ
- 漫画『One Piece』におけるキャラクターを 生かす工夫と作品に与える影響(日英比較)
- 名詞表現の語彙概念拡張に関する考察
2018年度
- 人間が音楽構成と詞へ与える効果の分析−−ピンク・フロイドの軌跡と音楽−−